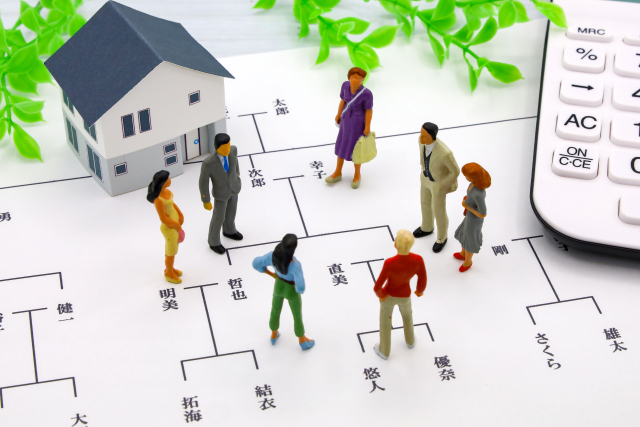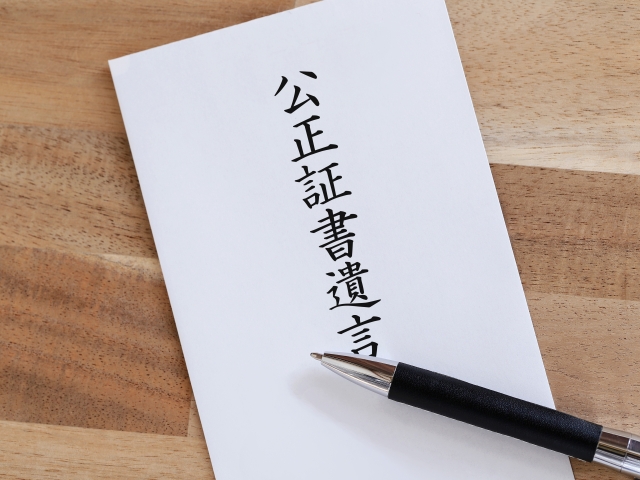昨日は「公正証書遺言」についてお話ししました。
→ こちらの記事をご覧ください
今日は、「どんな人が遺言書を書いた方が良いのか」について考えてみたいと思います。
「遺言書は特別な人が書くもの」と思っていませんか?
実はそうではなく、“自分の想いをきちんと残したい”と思うすべての方に関係のあるものです。
よく耳にするのが
「うちは揉めることなんてないから」
「まだ元気なのに、遺言書を書くなんて縁起が悪い」
「財産なんて、この家くらいしか無いから」
という言葉です。
けれども、いざという時に“自分の希望”をきちんと形にしておくことは、
残されたご家族にとっても、実はとても大きな安心につながります。
遺言書を書いた方が良いとされる主なケース
1. ご家族や相続人が複数いる場合
誰に何を残すのか、話し合うだけでは誤解が生じることもあります。
遺言書で明確にしておくことで、トラブルを防ぐことができます。
2. 配偶者や子ども以外に財産を渡したい場合
たとえば、世話をしてくれた親族・友人・事実婚のパートナーなど。
法律上の「相続人」以外の方に想いを伝えたい場合は、遺言書が必要です。
3. ご自身名義の不動産をお持ちの方
家や土地などは分けにくい財産の代表です。
誰に引き継ぐのかを遺言で指定しておくと、手続きがスムーズになります。
4. 子どもがいないご夫婦
配偶者がすべてを相続できるとは限りません。
遺言書を作成しておくことで、望む形で財産を残しやすくなります。
5. 再婚している、または前妻・前夫との間に子どもがいる方
相続人が複数の家庭にまたがる場合、思わぬトラブルが起こることもあります。
気持ちを明確に伝えるためにも、遺言書で意思を示しておくことが大切です。
6. 会社を経営している・自営業をしている方
事業用の財産をどう引き継ぐか、後継者をどうするか――。
あらかじめ方向を示しておくことで、家族や従業員を守ることにもつながります。
7. 将来の判断力に不安を感じている方
「認知症になる前に」「しっかり考えられる今のうちに」
そう思った時が、実は一番の作りどきです。
8. 単身で暮らしている方
ご家族がいない、または相続人がいない場合でも、
大切な友人やお世話になった方、地域や団体に財産を託すことができます。
そのような意思を形にするには、遺言書を作成しておくことが欠かせません。
9. 遺贈や寄付を考えている方
自分が築いた財産を、家族以外の誰かや社会のために役立てたい――。
そんな思いを実現できるのが、遺言書における「遺贈(いぞう)」や「寄付」です。
たとえば、福祉団体や動物保護団体、母校などへの寄付も、
遺言書に書き残すことで実現することができます。
10. 相続人の中に認知症の方がいる場合
相続が発生した後、相続人の中に認知症の方がいると、
遺産分割協議を進めるために「成年後見人」を選任する必要が出てくることがあります。
この手続きには時間も費用もかかり、ご家族の負担になることも少なくありません。
あらかじめ遺言書を作成しておけば、
ご自身の意思で分け方を決めておけるため、相続の手続きをスムーズに進めることができます。
※2026年1月現在、成年後見制度について見直しの議論が進んでいます。
本記事は現行制度(2026年時点)を前提に事例を用いて説明しています。
改正案の成立・施行日はまだ未定ですが、最新情報に基づき追記・更新していきます。
遺言書を書くことで得られる安心
遺言書を作ることは、「もしもの時」のためだけではありません。
「自分の想いを整理し、これからを安心して過ごすための準備」でもあります。
遺言書があることで、
- 残されたご家族が迷わずに手続きを進められる
- ご自身の希望を正確に伝えられる
- トラブルを防ぎ、家族や周囲との関係を守ることができる
といった安心につながります。
まとめ
遺言書は、特別な人だけのものではなく、
“自分の想いを残したい”すべての人のためのものです。
早すぎるということはありません。
「これからの安心のために、今の自分にできることを少しずつ整えていく」
その気持ちが、何よりも大切だと思います。
私自身も、行政書士として感じているのは、
“遺言書は人生のまとめではなく、これからを前向きに生きるための準備”ということです。
今日の記事が、「自分だったらどう書こうかな」と考えるきっかけになれば嬉しいです。
—————————————————————————————————————
行政書士 岡部暁子
小江戸川越の「行政書士岡部あき子事務所」より、
暮らしに寄り添う相続・遺言コラムをお届けしています。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別事情に対する助言には該当しません。
⇓