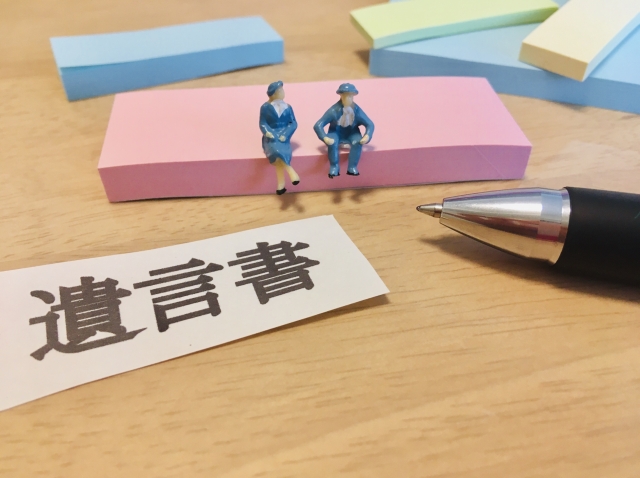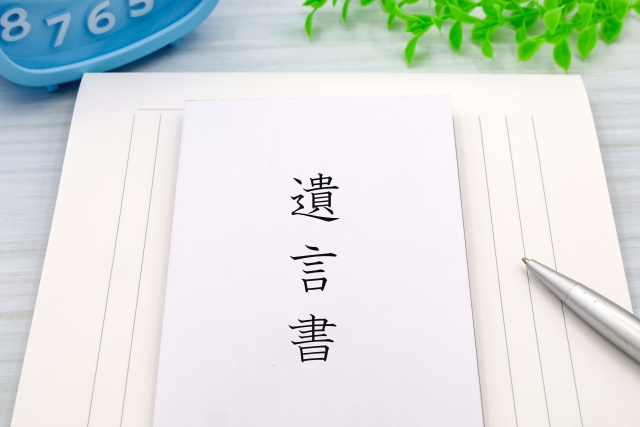ドラマでは、遺言書というと「大きな屋敷で開封される」「莫大な財産をめぐって家族が集まる」――
そんなシーンを思い浮かべる方も多いかもしれません。
でも実際の遺言書は、“特別な人のもの”ではなく、“自分の想いを大切にしたい人のもの”です。
家族への想いをきちんと伝えたい、少しでも負担を減らしたい、
そんな気持ちから作る方が増えています。
遺言書というと「家族のために残すもの」と思われがちですが、
実は自分のためのものでもあります。
自分の想いを整理し、これからの生き方を見つめ直すきっかけになるからです。
また、家族がいない方やおひとりで暮らしている方にとっても、
自分の財産や希望をしっかりと残しておくことは大切です。
「遺言書を作る=誰かのために残す」というより、
「自分の人生を自分の言葉で締めくくるための大切な準備」と考えると、少し気持ちが楽になるかもしれません。
ちなみに「遺言」という漢字、一般的には「ゆいごん」と読みますが、
法律用語では「いごん」と読みます。
この違いについては、また後日、もう少し詳しくご説明します。
遺言書には主に3つの種類があります
日本の法律で認められている代表的な遺言書は次の3つです。
それぞれの特徴を簡単に見ていきましょう。
自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん・いごん)
自分の手で書く、最も身近な遺言書です。
紙とペン、そして押印があれば作ることができますが、
内容に不備があると無効になってしまうこともあります。
手軽に作れる一方で、正しい形式や書き方に注意が必要です。
→ 詳しくはこちらの記事をご覧ください
公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん・いごん)
公証役場で作成する遺言書で、確実性と安全性が高いのが特徴です。
公証人が関与し、原本も公証役場で保管されるため、紛失や偽造の心配がありません。
行政書士はこの公正証書遺言を作成する際に、
文案の作成や、証人としての立ち会いをお手伝いすることもあります。
秘密証書遺言(ひみつしょうしょゆいごん・いごん)
自分で内容を秘密にしておきたい場合に選ばれる形式です。
内容は本人だけが知っており、封印した状態で公証役場に提出します。
ただし、この形式はあまり利用されることが少なく、
確実性という点では公正証書遺言のほうが安心です。
自分に合った遺言書を選ぶために
どの遺言書にもメリット・デメリットがあります。
「とりあえず自分で書いておきたい」のか、
「確実に家族に伝えたい」のかによって選び方も変わります。
行政書士は、それぞれの事情に合わせて、
どの形式が向いているかを一緒に考え、文案の作成をサポートします。
まとめ
遺言書は「もしものとき」ではなく、「これからの安心のため」に作っておくものです。
家族がいる人も、単身で暮らす人も、どんな立場の方にも「遺言書を残す意味」があります。
自分の想いをきちんと形にしておくことで、安心してこれからを過ごすことができます。
—————————————————————————————————————
行政書士 岡部暁子
小江戸川越の「行政書士岡部あき子事務所」より、
暮らしに寄り添う相続・遺言コラムをお届けしています。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別事情に対する助言には該当しません。
⇓