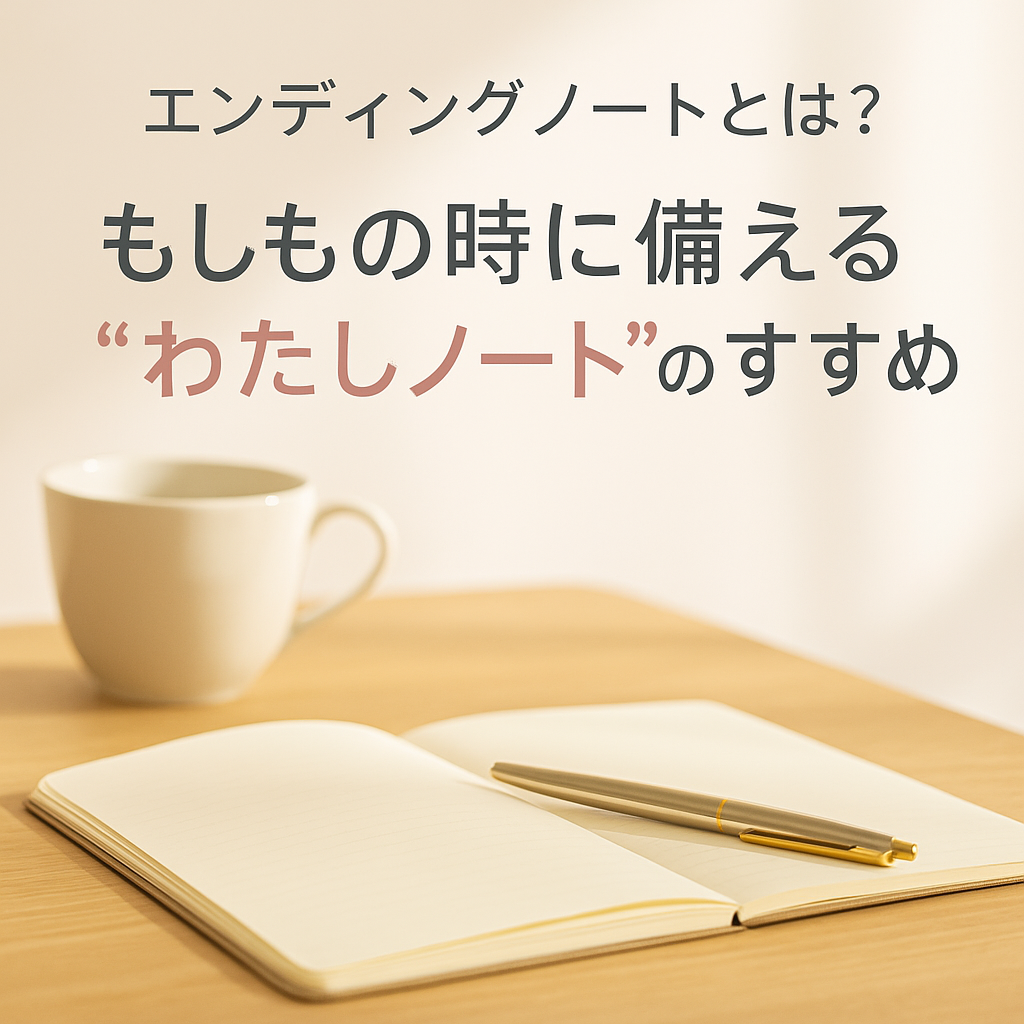「相続の話なんて、まだ早い」と思っていませんか?
親が元気なうちに「相続」や「遺言」の話をするのは、
なんとなく気が引ける…という方は多いと思います。
「縁起でもない」「まだそんな話をする年じゃない」と感じて、
つい後回しになってしまうのも無理はありません。
けれども、実際には 元気なうちにこそ話しておくことが大切 です。
それは「財産のため」だけでなく、家族の心の整理にもつながるからです。
私自身の経験から感じたこと
私自身も、家族の相続を通して感じたことがあります。
私の義父は、60代で心筋梗塞で突然亡くなりました。前日までは本当に元気だったのに。
そして義母は認知症を発症してしまい、
遺言や想いについて話す機会がないまま、亡くなってしまいました。
「2人は本当は何を伝えたかったのだろう」
「どうしてほしいと思っていたのだろう」
私は何も“聞けなかったこと”を後悔しました。
この経験から、
自分の親や、ほかのご家族には同じ思いをしてほしくない
という気持ちを強く持つようになりました。
話し合っておくことで防げるトラブル
相続に関するトラブルの多くは、
「お金」よりも「気持ちのすれ違い」から起こると言われています。
たとえば──
- 誰が何を引き継ぐのかがわからない
- 親の想いが伝わっていなかった
- 兄弟の間で“言った・言わない”になってしまった
こうしたことは、ほんの少し話しておくだけで防げるケースがほとんどです。
話し合っておくことは、「揉めないための準備」ではなく、
お互いを思いやるための時間 と考えると、少し気持ちが楽になります。
話すときのポイント
1.きっかけは自然に
「相続の話をしよう」と構えると、お互いに重たく感じてしまいます。
季節の変わり目や法改正のニュース、一緒に見ていたワイドショーの話題などをきっかけに、
「そういえば、うちの場合はどうなるんだろうね」と軽く話題に出すくらいがちょうどいいです。
私の両親の場合は、同年代の方がお亡くなりになられたことをきっかけに、
「うちもそろそろ考えないとかな?」と言うようになりました。
2.“財産の話”より“想いの話”から
最初から「誰に何を」と考えると難しく感じます。
まずは「過ごしてきた家をどう残したいか」や「みんなが困らないようにしたい」といった
想いの部分を話してみると、自然と方向性が見えてきます。
3.書面に残すことも大切に
話した内容をメモにしておくことで、後から「聞いていない」「忘れた」という行き違いを防げます。
その延長として遺言書を作成しておくと、より確実に想いを残すことができます。
行政書士は、そうした書面の整理や作成支援を行う専門家です。
「話す」ことは「思いやり」
相続の準備というと、何か特別なことのように感じるかもしれませんが、
実際には 家族の未来を安心にするための“思いやり” です。
まだ元気なうちにこそ、
「どうしてほしいか」「どんな形で残したいか」を話しておくことで、
残された家族が迷わずにすみます。
まとめ
相続の話は、亡くなった後ではなく 生きている今こそ 話しておくことが大切です。
お金の話ではなく、家族の想いを伝える時間 として、
少しずつ言葉にしてみてはいかがでしょうか。
遺言書はまだ早いと思っている方は、エンディングノートから始めると良いと思います。
次回はエンディングノートについて、お話ししていきたいと思います。
行政書士 岡部暁子
小江戸川越の「行政書士岡部あき子事務所」より、
暮らしに寄り添う相続・遺言コラムをお届けしています。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別事情に対する助言には該当しません。
⇓